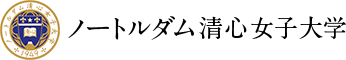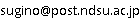| 1. |
2023/11/30 |
思考力・表現力の育成を目指し,ICTを効果的に活用する算数の授業づくり/令和5年度岡山県小学校教育研究会瀬戸内支会算数部会第1回研修会 |
| 2. |
2023/11/24 |
思考力・表現力を育成する算数科の授業づくり/令和6年度全国へき地教育研究大会(岡山大会)中間発表会 |
| 3. |
2023/11/21 |
数学的活動を通して数学的に考える力を育てる算数の授業づくり/岡山県小学校教育研究会算数部会冬季研修会(zoom) |
| 4. |
2023/11/16 |
主体的に考え,表現する子どもを育てる算数の授業づくり/令和5年度 兵小研東播磨・北播磨地区算数部会指定 算数教育研究発表会(多可町立八千代小学校) |
| 5. |
2023/08/22 |
算数科の授業づくりの実践②/揖龍教育研修所 第3回小学校算数科授業づくり実践講座(たつの市総合文化会館アクアホール) |
| 6. |
2023/08/01 |
算数科の授業づくりの実践①/揖龍教育研修所 第2回小学校算数科授業づくり実践講座(たつの市総合文化会館アクアホール) |
| 7. |
2023/07/25 |
算数科の授業づくりの基礎・基本/揖龍教育研修所 第1回小学校算数科授業づくり実践講座(たつの市総合文化会館アクアホール) |
| 8. |
2022/11/11 |
主体的・対話的な学びで深い学びを目指す算数の授業づくり/令和3・4年度岡山県小学校教育研究会浅口支会 指定 浅口市教育委員会 指定 研究会 |
| 9. |
2022/11/08 |
対話的な学びを通して,よりよい考えを実感する児童の育成/令和4年度岡山県小学校教育研究会瀬戸内支会算数部会第1回研修会 |
| 10. |
2022/10/26 |
「深い学び」のある算数の授業づくり~数学のよさを実感する子ども~/第42回大阪府公立小学校算数教育研究発表南河内大会 |
| 11. |
2022/10/19 |
主体的に学習に取り組み,共に学び合う児童の育成~算数科における数学的な見方・考え方を働かせる指導法の工夫~/県小教研算数部会研修会および小教研玉野支会算数部第2回研修会ならびに玉野市立鉾立小学校校内研修会 |
| 12. |
2022/08/24 |
「数学的な見方・考え方」を豊かにする算数の授業づくり/岡山県小学校教育研究会算数部会夏季研修会(岡山市灘崎文化センター) |
| 13. |
2021/11/11 |
対話的な学びを通して,よりよい考えに気付く児童の育成/令和3年度岡山県小学校教育研究会瀬戸内支会算数部会第1回研修会 |
| 14. |
2021/08/05 |
算数科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて/井原市学校教育研究会 夏季算数班会 |
| 15. |
2021/08/04 |
思考力・表現力を育てる算数の授業づくり~ICTを効果的に活用し,考えたくなる,話したくなる授業づくりの工夫~/津山市学校教育研究センター算数部会 |
| 16. |
2021/07/01 |
「主体的・対話的で深い学び」を目指す算数科の授業づくり/令和3年度岡山市教職員研修講座 |
| 17. |
2021/01/13 |
対話的な学びを通して,よりよい考えを追求する児童の育成/令和2年度岡山県小学校教育研究会瀬戸内支会算数部会研修会 |
| 18. |
2020/10 |
「考えたい」「伝えたい」を生み出す算数科学習/令和元・2年度 岡山県数学教育会・岡山県小学校教育研究会算数部会 倉敷市立乙島小学校 算数教育研究発表会 |
| 19. |
2020/10 |
どの子にも「わかる」喜びを味わわせる算数科の授業づくり/津山市学校教育研究センター算数部会研修会及び津山市立広戸小学校校内研修会(津山市立広戸小学校) |
| 20. |
2020/10 |
基礎・基本の確かな定着を図りながら思考力・表現力を育む算数科の授業づくり/小教研玉野支部算数部会及び玉野市立大崎小学校校内研修会 |
| 21. |
2020/10 |
対話的な学びを通して深い学びを目指す算数科の授業づくり/令和元・2年度 高梁市教育委員会指定 学力向上研究発表会(高梁市立成羽小学校) |
| 22. |
2019/08 |
「主体的・対話的で深い学び」のある算数科の授業づくり/井原市学校教育研究会算数班会研修会(井原市大江公民館) |
| 23. |
2019/08 |
「主体的・対話的で深い学び」を目指す算数科の授業づくり/岡山市教育研究研修センター小学校算数研修講座(ウェルポートなださき) |
| 24. |
2019/08 |
「深い学び」の実現を目指す算数の授業/岡山県小学校教育研究会算数部会夏季研修会(岡山西ふれあいセンター) |
| 25. |
2019/08 |
算数・数学科における全国学力学習状況調査,町学力テスト,授業等における課題から解決方法を考える/佐用町教育研究所算数・数学授業力向上研修講座(兵庫県作用郡佐用町役場) |
| 26. |
2019/08 |
思考力・表現力を育てる算数指導/津山市学校教育センター算数部会(津山市中央公民館) |
| 27. |
2019/07 |
「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す算数の授業づくり/小教研小田支会算数部会研修会(小田郡矢掛町立三谷小学校) |
| 28. |
2019/05 |
複式学級における学級経営と学習指導の充実/岡山県総合教育センター研修講座(岡山県総合教育センター) |
| 29. |
2018/10 |
「深い学び」のある算数の授業づくり/平成29・30年度井原市教育委員会指定 小学校教育研究発表会(井原市立大江小学校) |
| 30. |
2018/08 |
算数・数学科における主体的・対話的で深い学びにつながる授業のあり方/平成30年度佐用町教育研究所講座(兵庫県佐用郡佐用町役場) |
| 31. |
2018/08 |
算数科における主体的・対話的で深い学びの実現に向けて/井原市小学校教育研究部算数班講習会(井原市大江公民館) |
| 32. |
2018/05 |
算数科における「深い学び」のある授業の創造/岡山県小学校教育研究会算数部会研修会(岡山県立岡山朝日高等学校) |
| 33. |
2017/09 |
子どもの思考力・表現力を育てる算数の授業デザイン/第1回美浜町小学校授業力向上研修会(福井県三方郡美浜町歴史文化館) |
| 34. |
2017/08 |
「主体的,対話的で深い学び」を目指す算数・数学の授業づくり/平成29年度佐用町教育研究所講座(兵庫県佐用郡佐用町役場) |
| 35. |
2017/08 |
子どもの学力差に対応した算数の授業デザイン/第2回備前市教育研修所小学校算数部会研修会(備前市立片上小学校) |
| 36. |
2017/08 |
自分の考えをもち,伝え合い,学び合う授業づくり/平成29年度新見市小学校算数部会夏季研修会(新見市立草間台小学校) |
| 37. |
2017/08 |
全国学テから見える算数科の課題と授業づくり/第1回高浜町小学校授業力向上研修会(福井県大飯郡高浜町立高浜小学校) |
| 38. |
2017/06 |
「深い学び」の実現を目指す算数の授業デザイン/岡山県小学校教育研究会算数部会研修会(岡山市ウェルポートなださき) |
| 39. |
2016/12 |
思考力・表現力を高める算数授業の創造/平成28年度倉敷市小学校教育研究会算数部冬季研修会(倉敷市立茶屋町小学校) |
| 40. |
2016/10 |
キャリア教育につなぐ算数授業の創造/平成27・28年度岡山県教育委員会指定「奈義中学校区キャリア教育実践モデル開発事業」公開授業研究発表会(奈義町立奈義小学校) |
| 41. |
2016/08 |
算数の授業づくりに生かす教材研究の仕方/平成28年度岡山市教職員研修講座(百花プラザ) |
| 42. |
2016/08 |
子どもの思考力・表現力を育てる算数の授業づくり/第1回高浜町小学校授業力向上研修会(福井県大飯郡高浜町立和田小学校) |
| 43. |
2015/11 |
確かな学力を育成する「伝え合い学び合う」算数の授業づくり/平成27年度兵庫県小学校教育研究会算数部指定 中・西播磨地区小学校算数教育研究会(兵庫県佐用郡佐用町立利神小学校) |
| 44. |
2015/10 |
「学び合い」を大切にした算数の授業づくり/平成27年度但馬地区小学校算数教育研究大会(兵庫県朝来市立山口小学校) |
| 45. |
2015/10 |
学び合いを生かした算数の授業づくり/平成26・27年度加西市教育委員会指定学習指導研究発表会(兵庫県加西市立日吉小学校) |
| 46. |
2015/10 |
自立・協働を通して創造する算数の授業づくり/平成26・27年度岡山県小学校教育研究会浅口支会指定・浅口市教育委員会指定研究発表会(浅口市立鴨方東小学校) |
| 47. |
2015/08 |
教科書を活用した算数授業の改善/米子市小学校教育研究会算数部研修会(米子市立明道小学校) |
| 48. |
2015/06 |
アクティブ・ラーニングを生かした算数の授業づくり/岡山県小学校教育研究会算数部会研修会(岡山市灘崎文化センター) |
| 49. |
2015/06 |
確かな学力を育成する少人数指導/倉敷教育センター・第1回少人数指導担当教員研修講座(小学校・算数,中学校・数学)(倉敷教育センター大ホール) |
| 50. |
2015/04 |
啓林館算数教育実践学講座 第22回「拡大と縮小」 |
| 51. |
2015/04 |
啓林館算数教育実践学講座 第26回「学習の進め方」 |
| 52. |
2015/02 |
教科書を活用した算数の授業づくり/勝田郡小学校算数研修会(勝央町公民館) |
| 53. |
2015/01 |
教科書を活用した算数の授業づくり/津山市教育委員会・平成26年度第4回津山地区研究協議会(津山市役所東庁舎) |
| 54. |
2014/12 |
思考力・表現力を高める算数科の授業/倉敷市小学校教育研究会算数部冬季研修会(倉敷市立味野小学校) |
| 55. |
2014/11 |
学び合う教室をつくろう―魅力ある算数授業をめざして―/東播磨地区小学校算数魅力ある授業づくり実践研修(高砂市立高砂小学校) |
| 56. |
2014/10 |
思考力・表現力を育てる算数的コミュニケーション活動/岡山県小学校教育研究会算数部会並びに瀬戸内市教育委員会指定算数教育研究発表会(瀬戸内市立今城小学校) |
| 57. |
2014/08 |
思考力・表現力を育てる算数の授業づくり/津山市学校教育センター算数部夏季研修会(津山市久米公民館) |
| 58. |
2014/06 |
確かな学力の育成をめざす算数的活動を生かした授業づくりの工夫/岡山県総合教育センター・小学校算数研修講座(岡山県総合教育センター) |
| 59. |
2014/06 |
思考力・表現力を育成する算数の授業づくり/岡山県小学校教育研究会算数部会研修会(岡山市ウェルポートなださき) |
| 60. |
2014/04 |
啓林館算数教育実践学講座 第12回「小数の乗除」 |
| 61. |
2013/08 |
各学年2学期の授業づくりのポイント/加古川市教育委員会・教育研究所「算数の力を伸ばす研修講座」④(加古川市教育研究所) |
| 62. |
2013/08 |
算数の授業改善の具体的な方策/加古川市教育委員会・教育研究所「算数の力を伸ばす研修講座」③(加古川市教育研究所) |
| 63. |
2013/08 |
算数的コミュニケーションを育てる算数指導/明石市夏季算数科教育研修会(明石市立鳥羽小学校) |
| 64. |
2013/08 |
算数的活動、言語活動の充実を生かした授業づくり/加古川市教育委員会・教育研究所「算数の力を伸ばす研修講座」②(加古川市教育研究所) |
| 65. |
2013/08 |
算数的活動を取り入れた授業づくり/平成25年度豊岡市「授業づくり」研修会(豊岡市民会館) |
| 66. |
2013/08 |
算数的活動を生かした授業づくり/玉野市教育研修所小学校算数部研修会(玉野市玉小学校) |
| 67. |
2013/07 |
子どもにつけたい力と授業改善のポイント/加古川市教育委員会・教育研究所「算数の力を伸ばす研修講座」①(加古川市教育研究所) |
| 68. |
2013/04 |
啓林館算数教育実践学講座 第1回「分数と小数」 |
| 69. |
2013/02 |
思考力・表現力を育てる算数指導/平成24年度那賀地方算数・数学教育研究会算数科授業研修会及び教育講演会(和歌山県岩出市立岩出小学校) |
| 70. |
2012/12 |
算数的コミュニケーション活動の充実で授業改善を図る/倉敷市小学校教育研究会算数部第2回研修会(倉敷市立連島東小学校) |
| 71. |
2012/11 |
「言語活動の充実」を図り学力向上を目ざす算数の授業改善/倉敷市「授業力アップ支援事業」(倉敷市立菅生小学校) |
| 72. |
2012/08 |
新しい「算数的活動」を取り入れた授業づくり/平成24年度兵庫県豊岡市ブロック別・学年別研修「授業づくり」研修会(ウェルストーク豊岡) |
| 73. |
2012/07 |
「ことばの力」育成を目指す算数の授業づくり/県指定「ことばの力」育成事業(兵庫県丹波市立上久下小学校) |
| 74. |
2012/04 |
ノートルダム清心女子大学教員免許状更新講習 算数 |
|
10件表示
|
|
全件表示(74件)
|